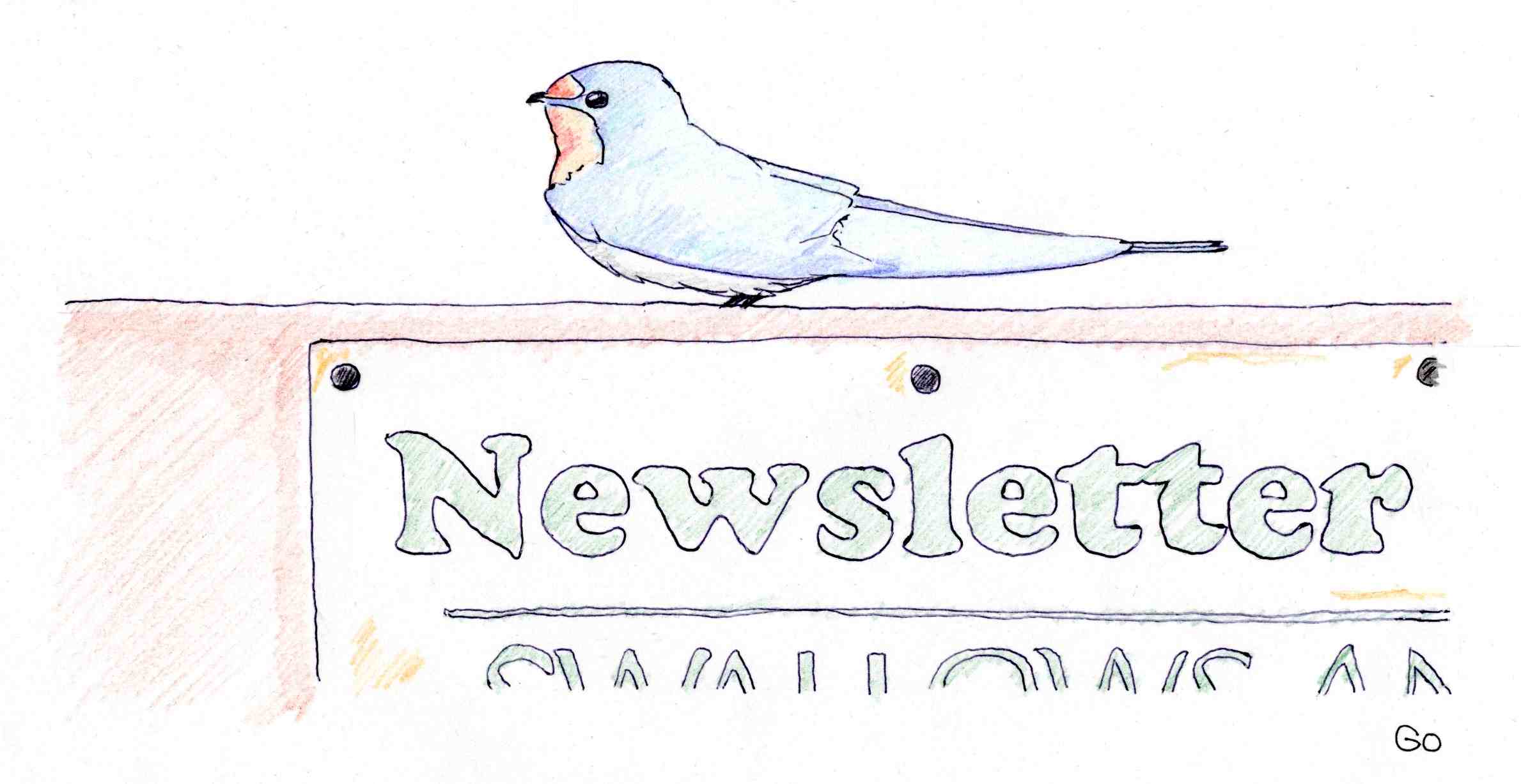
音をたよりに文章を練る. May 31 2015
英語で話しているときに覚えた言葉、とくに固有名詞をカタカナにするのは、かなり苦手。どんなに工夫しても、どうやっても、記憶の中にある彼やそれ、あの場所とつながらない。
Mongolia で出会った「Peter」は、頭の 'P' にアクセントがあり、t は n に近いけど t。'er' はあってもなくてもいいが、どちらかというとないに近い。でも、口にしないけれど、舌をたてに丸めながら (推定) 口をとがらせる。
これは、Mongolia へ一緒に行った Jim が彼を呼ぶときの言葉。たぶん米国東部、北の方のアクセントだろう。
これを「ピーター」と書いてしまうと、まるで別人。無理にカタカナにするとピナ(ー) かピタ(ー) だけど、これじゃなんだか地中海のパンみたいだし、うしろの括弧マイナスはなんだと聞かれてしまうだろう。
「Russia」も、ぼくが出会った地元の人たちがつかう、あるいは Mongolia で出会った人たちが複雑な感情を込めてつかう Russia。
'R' を口に出す前にお腹に力を入れ、思いっきり空気の塊を出しながら、喉を鳴らすように、あるいは大阪の友だちが「なんじゃ、おら」とクダをまくときの巻き舌の「ら」のような感じで R を強調し、それをうまくうけて、'ssia' も続ける。日本語的に最後の「あ」もはっきり口に出す感じ。
だから、日本人どうしで話しているときは極力固有名詞を最小限にし、声にだすときはできるだけ日本語的な音にする (むかし好きだったマンガにでてきた、オモロイおっさんたちとカブリませんよーに..)。でも、問題は日本語の文章にするとき。カタカナにすると、そこが違和感いっぱいで、うまくかけない。
そんなことなどどうでもいい言葉もあるけど、音がとても大切という言葉もたくさんある。そして (これは人によってちがうのでいいと思うけれど) 文章とは、その大切な音がつくりだす波のようなもの。
ここまでかいて自分が文章をつくるときに、視覚と同じくらい、音を大切にしていることに気づいた。たしか William Zinsser は文章を練るとき、そして文章を完成させるときには、声にだして読み上げることが効果的と言っていた [1]。
そういえば、英語の文章を何とかつまらずに、日本語と同じようにかけるようになったのは、頭の中に声が聞こえてくるようになったときだった。
「いい文章」(のひとつの形) とは、頭の中に浮かんでくる、文字が示す意味や論理の波だけでなく、それに音の波が組み合わさったバランスとわずかなアンバランスを、文字という記号で客観的に表現できているときではないだろうか (そして、このバランスとアンバランスをどうつくるかと、それを文字情報にどう翻訳するかが、個性の出しどころ)。
なんだか当たり前のような、でも大事なことのような、やっぱりどうでもいいような大発見 (仮)。
- Zinsser W. 2006. On Writing Well. Collins, Sydney