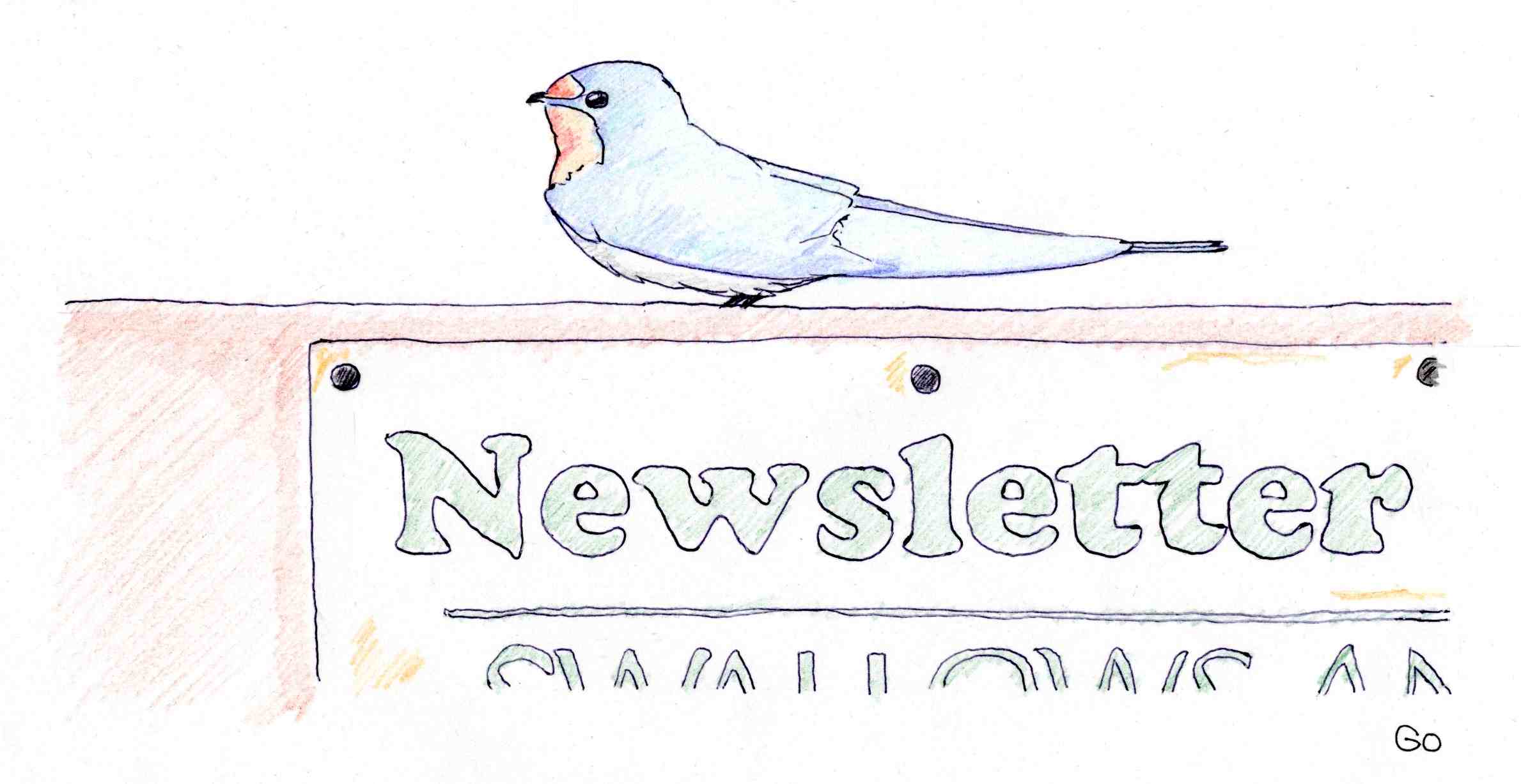
ゾウの国
彼は、スリランカのポロンナルワという遺跡の町にある、2番目に評判だと聞いたホテルで働く2番目だかにえらいホテルのスタッフだった。
グレイ・ヘアーのようすから、年齢はたぶん50代後半。姿勢もまっすぐで、語尾につける「Sir」もかなり使い込んだ自然さを備えていた。
他のスタッフは青灰色のネルージャケットのような制服なのに、彼はいつも、深いエンジのベストにボウタイのスーツだった。
*
たしか夕食のあと、ホテルの前に広がる湖のようなタンク (1500年前につくられた大きな貯水池) の水辺に置かれたテーブルで、ぼくたちは、スリランカじゃないと飲めない滑らかな味のミルクティーを飲みながら、水面すれすれに飛ぶ、飛行艇のようなペリカンを眺めていた。
彼は、スリランカの人に特徴的なはにかんだような笑みをたたえながら、まっすぐこちらのテーブルへと歩いてきて、
「このレンズの汚れは、取れないでしょうか..」
と、20年は使い込んだにちがいない双眼鏡をもってきた。10年くらい前、ドイツの友人から譲り受けたものだそうだ。
ぼくができるかんたんな分解もやってみたけれど、それは心配したとおりのカビだった。だから、レンズとプリズムに生えたカビをとるのはたぶん無理だと、言うしかなかった。熱帯では、よほどの手入れをしないとこうなってしまうのだろう。
「やはり、そうですか」
双眼鏡を両手にとって見つめるその姿から、彼がどれくらい双眼鏡を大切にしているかが伝わってくる。
もういちど、やはりそうですかと、自分に言い聞かせるようにぼくの同意を得ると、その双眼鏡のストラップを首にかけ、目の前に広がる水辺へと歩いていった。
*
いつも双眼鏡で見るのを楽しみにしている場所があるようで、2キロくらい離れたタンクの対岸のポイントを、手慣れた様子でひとつずつ確認している。
そしてすぐにこちらに振り向いて、対岸のあの左端に見える草地に野生ゾウの家族がいますよと、大きすぎない明るい声で、指差しながら教えてくれた。
*
テーブルの上に置いてあった自分の双眼鏡でのぞくと、森の中から出てきた大きな雌ゾウが2頭、ゆっくりと草地の先にある水辺に向かって歩いている。
そして、小さな子ゾウが、その2頭の陰から飛び出して、水の中へ。水しぶきが子ゾウをつつむ。雌2頭は、慌てる様子もなく、鼻でリズムをとるように、ゆっくりと子ゾウのもとへ。
お腹まで水につかった子ゾウが気にする方に双眼鏡の視野をずらすと、雌たちよりもふたまわりは大きなゾウがいる。森の木の葉を食べているのか頭や牙は見えなかったけれど、たぶん雄だろう。森の縁が、大きく揺れている。
*
湿原の植物に囲まれ、無数のコウノトリやクイナの住処になった1500歳のタンク。ジャングルに覆われ、崩れた塀の上を、ハヌマンラングールの群れがゆっくりと歩く宮殿。
そしてたぶん毎夕、対岸の野生ゾウ家族と会うことを楽しみにしているホテルのアシスタントマネージャーと、スリランカで寿命を終えようとしているドイツ生まれの双眼鏡。
*
そういうことが重なって、スリランカは、今でも1番好きな国のひとつ。あのユーラシアの真ん中にある、草原を生きる人たちがつくった国と同じくらいに好きな国のひとつ。
そして、夕焼けがきれいな日に自分の双眼鏡を見ながら、ふと思うことがある。彼は、新しい双眼鏡を手にすることができたろうか。
(December 1, 2015)