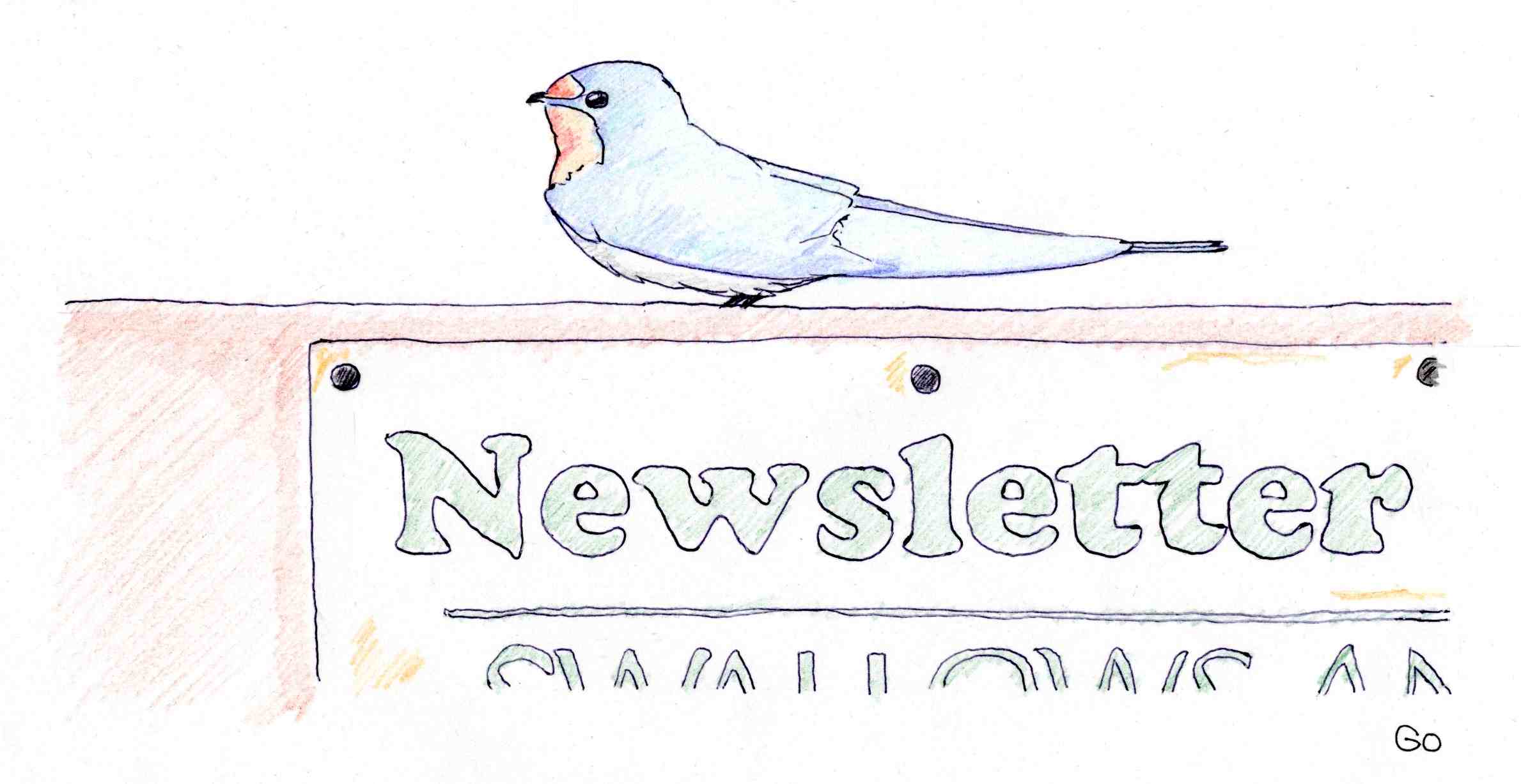
スケッチ (その2). July 31 2015
地元のまちに、O 美術館という小さめの美術館がある。残念ながら数年間閉館したままだけど、ここは、理想の美術館のひとつ。
絵が多すぎず、どの絵も思う存分みることができて、(たぶん、この美術館の基礎をつくった人にとって) 特別な何人かの作品が集められている。そして自由にスケッチできた [1]。
この美術館には Raoul Dufy がたくさんあった。というか、Dufy と数人の作品以外はあまりなかった。何となく寄ったこの美術館で、ぼくは初めて本物の Dufy をみて、彼の色と線にとても驚き、でもそれが絵になっていることを不思議に思った。
ぼくは美術館で、よくスケッチする。作品をみているうちに、自分もかきたくなるからだ。たくさんは無理だし、くたびれるから、だいたい1回にひとつかふたつをスケッチする。
スケッチを何度か繰り返すと、その絵をある程度、ソラで思い浮かべられるようになる。そうなるくらい気に入ったものは、美味しい珈琲を飲める珈琲屋なんかで、自分が納得するまで自分でかきなおしたりする。
その絵はもちろん、もとのとはちがうぼくのしょぼい絵なんだけれど、何度かかくうちに、ちょっと本物に近づけたかな、と思うときがある。でも、もとの絵を見直すと大事なところがちがっていて、やっぱりこのおっさんスゴイなと思いながら、またかきなおす。それを繰り返すことで、絵が自分の一部になる感覚がある。
そんな感じで Dufy を、いつもかいていたときがあった。絵をみて感動したという部分もあったからだけど、なぜ彼の絵がいいのか、理解できなかったという部分も大きい。
スケッチしながら理解したことを文字にするのは難しいけれど、分かったと思うことをあげると、たとえば一見、平面に線を並べたようにみえる絵が、実は立体感をしっかり隠しもった絵であること。
あるいは、かきたいもののいちばん大切な線は、まわりのものとの位置関係によってダイナミックに変化すること。
そして、絵の中に一か所だけ、なんでこんなところにあるんだという、たとえば赤い点が打たれているとき、それが、そこに赤を打つという最初からの全体計画 (?) のもとにかいた可能性が高いこと。
本物の絵や彫刻をスケッチしていると、それをつくった人たちの声が聞こえてくる。人どうしが音声や手話で会話するように、スケッチは、人が絵や彫刻と会話するひとつの道具で、繰り返すことでだれもが使えるようになる、コミュニケーション手段ではないかと思っている。
- もしかすると、スケッチを黙認してくださっていただけかも知れません。もしそうだとしたら、受付や部屋にいた美術館の方々に、心から感謝です。