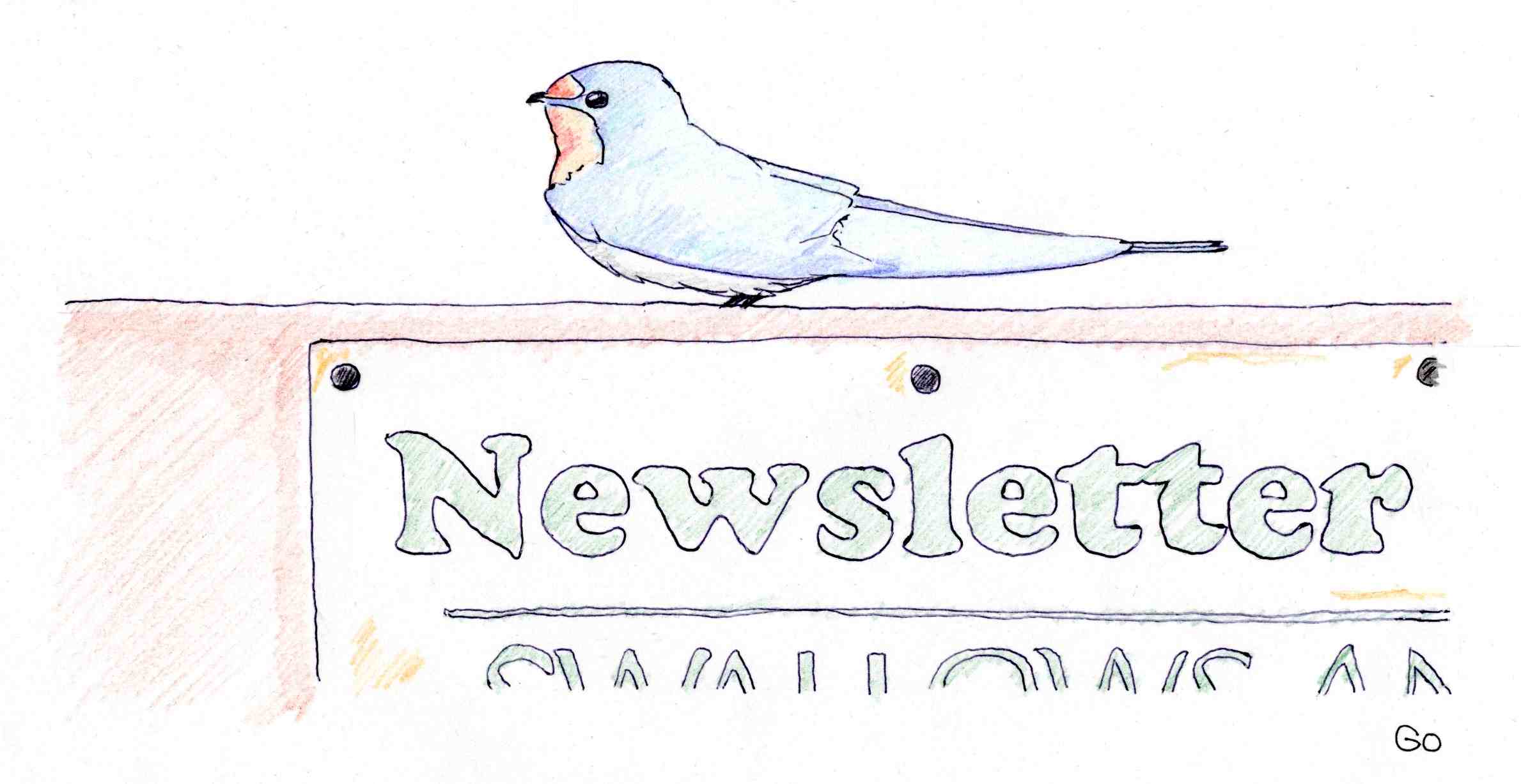
Huh mountain
大きな自然を前に、声すら出ないほど感動したことが、一度だけある。
たしか場所は、Huh mountain。「Huh」を頑張ってカタカナにするとホフ。モンゴルの名前だから、最初の「Hu」を思いっきり強く、喉も使って発音する。大ざっぱに言うと、ユーラシア大陸の真ん中あたりに聳える、太平洋と北極海の分水嶺。
大切な場所なので、あとで Google したりしなかった。だから、この英語のスペリングはちがってるかも知れないけど、ぼくにとって理想的なロシアン・イングリッシュを話す Chuuka がそう教えてくれたのだから、それでかまわない。
まあ、とにかくぼくたちは、黒いランドクルーザーと赤いハイラックスで、毎日数100キロを移動しながら、アネハヅルとマナヅルの調査をしていた。
90年代のモンゴルは、ロシアとの関係が悪くなったせいで、国外からの原油供給のほとんどが止まり、国中がオイルショックに苦しんでいた。首都のウランバートルでは、日に2時間しか電気が来ない。飛行機からは草原に浮かぶ空中都市に見えたロシア式の都市は、オーブンも湯沸かし器もすべて電気だったし、薪など手に入らない場所だったから (だって森がない)、その深刻さは半端じゃなかったろう。
そんな中の野外調査の準備も、かんたんなものではなかったけど、ぼくたちを受け入れてくれたモンゴルの人たちは、何だか大らかに、電気のない生活を楽しんでいるようにも見えた。まあ、調査に出てしまえば、どのみち電気など必要ないのだけれど。
*
Huh mountain に着いたのは、そろそろ昼ご飯にしようかという時間だったと思う。車を降りた Bold さんは、ベンチのような平らな岩に、痛めた腰をかばいながら座り、Peter と Jim、そしてぼくの外国人メンバー3人を自分の前に立たせ、手にもった杖のような棒で地面に線を引く。引き終わるか終わらないかのうちに、上目づかいに微笑みながらぼくたちの顔を見て、この線のこっちに落ちた雨は北極海、こっちに落ちた雨は太平洋に流れて行くんだと、流暢なロシア語で話してくれた。
ぼくの頭の中では、この地面に降った雨粒が小さな流れになり、それがすぐ、きのうの午後にみんなでジャンプして遊んだ、100キロ東の美しい箱庭のような渓谷の小川にまで育ち、そこから一気にズームアウトして大きなユーラシア大陸、その北にある北極海や、その南にある太平洋に流れ込む大河の絵になった。
Bold さんは、自分の話が終わると、ぼくらの左うしろの方を棒で指し、行っておいでという手振りをしたあと、ゆっくりこちらに背を向け、後ろに控えていたモンゴル人スタッフに向かって、さあチャイでも飲むかと両手を広げた。
*
ここから歩いて10分程度のところに、ピークがあるらしい。
なんでぼくらだけなんだと、少年のように愚痴る Jim を先頭に、ピークを緩やかに左へ巻きながら登る白っぽい砂地の道を、大またに歩いた。そして、このあたりかなあと Jim の声が聞こえたところで、一気に視界が開ける。
*
見渡す限りの草原と湿原。風はそれほどないはずだったけれど、地鳴りのような音が、ずっと鳴り響いていたのを覚えている。そのものすごい迫力と、眼下に広がる風景の大きさが、一緒になってどんどん胸の中に入ってくる気がした。
360度見渡せるこの山頂から、どれくらい遠くまで見えるのだろう。Bold さんの魔法にかかったぼくらには、北極海と太平洋さえ見える気がした。
ぼくらのハイラックスのドライバーが「さよなら Onnon」と覚えたての英語できのうの午前に別れを告げた Onnon 川が北東の方向、はるか遠くに見えた。その一部には、黒い雲が張りついていて、その下が灰色にけぶっている。たぶん夕立のような雨が強く降っているのだろう。
その黒い雲のすぐとなりには、もう強い日がさしていて、湿原の草が、明るい緑色に輝いている。その先のベージュ色の小さなパッチは、おとといの夕方、低い木の柵の向こうに見えたロシア側にある国境の村にちがいない。子育てを終えたアネハヅルの群れが、柵の向こうとこちらを行ったり来たりしていたのが目に焼きついている。
木の柵に両肘ついてこちらを見ているロシアの農夫に、この地域で育ち、やがて鳥の研究者になった Tsuveen が何やら話していた。たぶん今年の作物のなり具合と、ディーゼルの調達先をたずねているのだろう。調査以外のぼくたちの、その日一番のテーマは、底をつきかけている燃料の確保だった。モンゴルの草原には、もちろんガソリンスタンドなんか、ひとつもなかった。
*
うしろにいた Jim に呼ばれて振り返ると、彼の指さす先にたくさんの稲妻が見えた。そばで見れば高くそびえているはずの積乱雲が、その上に広がる深い青空の下で、とても小さく低く見えた。
3日前の昼食のとき、川辺で出会ったトルネードを思い出す。それは、川を渡ったぼくたちのゴムボートを何キロか先まで一気に運び、もとの岸に戻るためにぼくたちは、川を泳いで渡った。重い調査器具を頭に乗せて、一生懸命泳ぐおたがいの姿をみて、こらえきれずにみんなで大笑いした。土手にいたドライバーたちも、お腹をかかえながら笑った。
その川は、たしかあの方角。ちがうかも知れないけど、それらしい大きく蛇行する川面が、今は、強い太陽の光を眩しくはね返している。
そんなはずは絶対にないけれど、大きな青空の下、重い灰色の雲から稲光が走る風景は、はるか何億年も前のものに見えた。そんなはずは絶対にないけれど。
そして、気がつくと、涙が溢れていた。Peter たちに見られないように、それを拭ってみたのだが、次から次へと涙が出てきて、もう、どうでもよくなって振り返ると、2人とも泣いていた。
どれくらいの時間、3人が立っていたかは覚えていない。Jim が「行こうか」と言ったとき、やっと地球に、いや、今の時間に戻ってきた気がした。
*
そのあと、チャイを満喫した Bold さんたちと合流し、片言のロシア語で「ありがとう、よかった」とだけ言ったのを覚えている。
西へ向かって走り始めたハイラックスの中で、ドライバーが彼お気に入りの Eagles の曲を流し始める。いつもなら Peter がイントロも終わらないうちに止めてしまうのだが、あの時はそうしなかった。
Mongolian steppe に不似合いで時代遅れの Hotel California が、きっと最高に胸にしみたんだろう。
(October 12, 2015)